海外駐在・赴任者のための資産運用術を紹介|NISAやおすすめの運用プランを解説!

海外駐在や赴任をきっかけに、日本にいたときと同じように投資や資産運用ができないことを知り、戸惑っている方は少なくありません。特に30代〜50代の駐在員やそのご家族からは「NISAやiDeCoは使えないの?」「日本の証券口座はどうなる?」といった声が多く寄せられます。
非居住者になると金融制度や税制が変わるため、日本にいたときと同じ方法では運用できないケースがあります。一方で、現地口座での外貨預金や海外積立投資、海外ETF、不動産投資、さらには仮想通貨など、駐在中でも選べる資産運用の選択肢は豊富です。
本記事では、海外駐在員・赴任者におすすめの資産運用方法をわかりやすく解説するとともに、NISAや証券口座の注意点、ライフスタイル別の運用プラン、そして落とし穴を回避するためのポイントをご紹介します。安心して資産形成するために参考にしていただけると幸いです。
Contents
海外駐在・赴任者でも可能な主な資産運用方法【5選】

海外駐在や赴任中でも取り組める資産運用方法はいくつか存在します。日本に比べて制限される制度もありますが、選択肢を知っておくことで安定した資産形成を目指せます。代表的な方法としては、以下の5つが挙げられます。
- ・現地口座を利用した外貨定期預金
- ・定期積立でリスク分散できる海外積立投資
- ・海外ETFや外国株式を活用した運用
- ・日本または駐在国での不動産投資
- ・仮想通貨や金などの現物資産への投資
それぞれの特徴や注意点を順番に解説します。
1. 現地口座での外貨定期預金
外貨定期預金は、駐在国で銀行口座を開設できるのであれば手軽に始められる資産運用の方法のひとつです。現地通貨で運用するため、金利水準が日本より高い国では利息収入を得やすいというメリットがあります。
ただし、為替の変動によって受け取る金額が減ってしまうリスクもあるため注意が必要です。短期的には円高・円安の影響を受けやすいため、長期的に運用する、もしくは複数通貨に分散するといったリスクヘッジが必要です。安全性が高く比較的シンプルな方法なので、初めて海外で資産運用を始める駐在員にも向いています。
2. 海外積立投資
海外赴任者に人気の高い資産運用のひとつが、海外積立投資です。毎月一定額を積み立てることで金額を分散し、長期的に安定した資産形成を目指せます。現地通貨や米ドル建てで運用できるため、為替リスクを活用して資産を増やせるのも魅力です。
ただし、契約期間が長期に及ぶことや解約時の手数料が発生するケースもあるため、目的や期間を明確にして選ぶことが大切です。
海外積立投資プラン(積極型投資)
株式や新興国ファンド、最近では人気のビットコインファンドなど値動きの大きい商品を組み合わせ、長期で高いリターンを狙うプランです。短期的な変動リスクは高いものの、20年以上の駐在や教育資金・老後資金の準備に適しています。
元本確定型海外積立投資プラン(安定投資型)
満期まで運用すれば元本保証がある商品で、安定的に資産を守り、場合によっては次世代に資産を確実に継承したい人向けです。リターンは約5〜6%と限定的ですが、安全性を重視したい駐在員や配偶者に人気があります。
3. 海外ETF・外国株投資
海外ETFや外国株投資は、駐在中でも効率的に資産を増やせる方法として注目されています。米国市場を中心に幅広い銘柄へ投資できるため、低コストで国際分散ができるのが魅力です。
一方で、日本の証券口座は非居住者になると利用制限がかかるため、現地証券口座の開設やオフショア証券会社の活用が必要になるケースがあります。投資先や金融機関の選び方によってリスクや手数料が変わるため、事前の情報収集は必須です。制度や税務処理は複雑ですが、安定的に資産を成長させたい駐在員にとって、有力な選択肢となり得ます。
4. 日本または駐在国での不動産投資
不動産投資は、海外駐在員にとって資産の安定的な運用手段として選ばれることが多い方法です。日本国内の物件であれば馴染みやすいですが、管理を委託する必要があり、固定資産税や相続税など税務面での負担も考慮する必要があります。
駐在国での不動産購入は、現地の法律や外国人規制があるため、事前に確認することが欠かせません。また、通貨や市場の動向によって資産価値が左右される可能性もあります。将来的な居住や家族の生活基盤として活用できる利点もありますが、購入に踏み切る際は専門家のアドバイスを受けながら進めるのが賢明です。
5. 仮想通貨・現物資産などへの投資
仮想通貨や現物資産への投資は、海外駐在中でも取り組みやすい選択肢の一つです。代表的な仮想通貨にはビットコインやイーサリアムがあり、取引所を通じて現地からでも購入できます。ただし、価格変動が激しく、税務申告の取り扱いも複雑なため、資産全体の一部にとどめるのが現実的でしょう。
現物資産では、金やプラチナといった貴金属のほか、酒類や美術品など代替性のある資産を保有するという方法もあります。たとえば、金は世界中で古くから価値があるものとして扱われ、換金性が高いことが特徴です。通貨の価値が不安定な国に滞在する駐在員にとって「守りの資産」として人気があります。
一方で、酒類や美術品は管理・保管コストが発生しやすく、購入時の知識が求められます。仮想通貨・現物資産ともにリスク分散の一環として少額から取り入れると、より安心感を持って運用できるでしょう。
人気のiDeCoやNISAは海外駐在中にできない?資産運用とその理由

日本にいるときには定番の資産運用手段として多くの人が利用しているiDeCoやNISAですが、海外赴任や駐在に出ると非居住者の扱いとなり、これらの制度は利用できず積み立てを続けられないケースがほとんどです。
「続けていてもバレないのでは?」と考える人もいますが、金融機関や税務署はマイナンバーや海外転出届を通じて居住状況を把握できる仕組みになっています。日本と同じ感覚で運用を続けると、思わぬリスクやトラブルにつながる可能性があるため注意しましょう。
ここからは、利用できない理由や証券口座が凍結されるケース、また海外でiDeCoやNISAの積み立てを続けている場合、どのような仕組みでバレてしまうのかを解説します。
NISAやiDeCoが使えない理由
NISAやiDeCoは、日本国内に住んでいる居住者を対象とした制度です。そのため、日本に納税義務を持つ居住者だけが利用できる仕組みで、海外に駐在・赴任して非居住者となった時点で原則利用できなくなります。NISAの場合は、証券会社に登録している住所が海外になった時点で新規取引が停止され、積み立て設定も原則継続不可能です。
一方、iDeCoは年金制度の一部として位置づけられており、掛金拠出は国内での所得を前提に設計されています。そのため、海外赴任中は拠出ができず、一時的に「加入者資格喪失」となるのが一般的です。
帰国後に再開は可能ですが、駐在期間中は積み立てが途切れる点に注意が必要です。つまり、非居住者になると法的に利用が制限されるため、継続利用は現実的ではない制度です。
日本の証券口座が使えなくなるケース
海外赴任や駐在により日本で「非居住者」となった場合、多くの証券会社では証券口座の利用に制限がかかります。特に大手ネット証券では、非居住者が口座を保有すること自体を認めていないケースがあるため、海外転出の届け出を行った段階で口座が凍結され、新規取引や積み立てができなくなります。
既存の保有株式や投資信託は維持できることもありますが、保有している資産によっては放置しているままだと売却を求められたり、出金に制限がかかる可能性もあるため注意が必要です。一方、一部の証券会社やオフショア口座では非居住者の利用を認めている場合があり、駐在員の多くはそのような金融機関を利用して資産運用を継続しています。
つまり、海外に出ると「今まで使えていた口座が突然使えなくなる」ことがあるため、事前に各証券会社の対応を確認し、代替手段を検討しておくことが重要です。
税務署や金融機関に「バレる」仕組み
海外赴任中にNISAや証券口座を「そのまま利用し続けてもバレないのでは?」と考える人は少なくありません。しかし、金融機関や税務署は海外居住を把握できる仕組みを持っています。まず、海外転出届を提出すると住民票が消除され、税務上は非居住者として扱われます。この情報は金融機関にも共有されるため、取引の継続が難しくなります。
また、マイナンバー制度や国際的なCRS(共通報告基準)により、海外の銀行口座や投資状況が各国の税務当局間で自動的に交換される仕組みが整っています。さらに最近では、大手証券会社のハッキングを受けて安全性を高めるための2段階認証が強化され、日本国内の携帯番号にOTPが届くなど、これまでできていたことが不可能になる事例も耳にします。
つまり、海外で隠れて運用を続けても、ITセキュリティの強化や税務当局への情報連携により発覚リスクは高く、万が一発覚した場合、追徴課税やペナルティを受ける可能性もあるため、ルールを守って運用することが最も安全といえるでしょう。
海外駐在員におすすめのライフスタイル別資産運用プラン3選

海外駐在員といっても、赴任期間や家族構成、資産運用の目的は人それぞれです。短期的に資産を増やしたい人もいれば、教育資金や老後資金を計画的に準備したい人もいます。ここでは、代表的なライフスタイルに合わせた運用プランを3つご紹介します。
① 長期駐在&家族持ちで教育資金と老後資金を積み立てたい人
長期での駐在が決まっている方や家族を帯同している方は、教育費や老後資金といった将来に向けた長期的な資産形成が重要です。特に、子どもの進学費用や海外留学費用は想定以上にかかることも多いため、早めに準備を始めることが安心につながります。
代表的な手段としては、海外積立投資や現地口座での外貨定期預金が挙げられます。海外積立投資は時間分散が効き、20年単位で運用することで大きなリターンを期待できます。
一方、外貨定期預金は一定の資金拘束はあるものの、リスクを抑えながら着実に資産を積み上げられるのが魅力です。両者を組み合わせることで「成長性」と「安定性」のバランスを取りやすくなります。長期的なライフプランを見据えて積み立てを続ければ、帰国後の生活設計にも余裕が生まれるでしょう。
② 駐在期間が短い&独身で流動性重視の資産運用をしたい人
数年程度の短期赴任や独身生活の場合は、将来の予定が変わりやすいため「流動性」を意識した資産運用が望ましいです。必要なときにすぐ現金化できる商品を選ぶことで、帰国後の資金移動やライフプランの変更にも柔軟に対応できます。代表的な方法としては、海外ETFや外国株式への投資が挙げられ、比較的少額から始められる点も魅力です。
また、外貨預金やMMF(マネー・マーケット・ファンド)を組み合わせれば、為替を活かしながら資産を流動的に保てます。長期積立型に比べると大きな利益は得にくい一方、自由度の高さと資金移動のしやすさは大きなメリットです。
将来的に住む場所やキャリアが変わる可能性を考えると、短期駐在者には現金化のしやすい運用が現実的な選択肢となるでしょう。
③ 資産の一部を守りながら運用したい人
駐在中でも「大きなリスクは避けたい」「資産を減らさず守りたい」と考える方には、安全性を重視した運用が向いています。代表的な方法としては、元本確保型の海外積立投資や債券系ファンドがあり、安定的な利回りを期待できるのが特徴です。
たとえば、一定期間の運用を前提に元本保証が付いている商品であれば、急な市場変動が起きても資産を大きく減らす心配がありません。また、国債や社債など信用度の高い債券を組み込むことで、ポートフォリオ全体のリスクを下げ、株式や世界のREITなどで利回りを確保する部分を組み入れることで、資産増加のチャンスもしっかり得られます。
さらに、金やプラチナといった現物資産を一部組み合わせることで、インフレや通貨下落への備えにもなります。リターンは限定的ですが、家族を持つ駐在員やリタイア後の生活を意識する方にとって、安心感のある選択肢となるでしょう。
海外駐在中の資産運用で気をつけるべき3つの落とし穴

海外駐在中の資産運用には、日本にいるときには想定していなかったリスクが潜んでいます。非居住者になることで税制や証券口座の利用に制限がかかるほか、現地金融機関とのやり取りでは言語や制度の違いが障害となることもあります。
さらに、駐在員を狙った詐欺まがいの商品や高額手数料の投資案件もあるため注意が必要です。ここからは、特に注意すべき3つの落とし穴について説明します。
非居住者に課される税制・口座制限
海外赴任や駐在で「非居住者」となると、日本で利用できる金融制度や口座に大きな制約が生じます。たとえば、NISAやiDeCoといった税制優遇制度は非居住者になると利用できず、新規積立や掛金拠出ができなくなります。
また、多くの日本の証券会社は非居住者の口座保有を認めていないため、海外転出の届け出を行うと既存口座が凍結され、新規投資ができなくなるケースも少なくありません。さらに、非居住者は国内所得に対してのみ課税される一方で、海外資産に関しては駐在国の税制が適用されるため、国によっては二重課税のリスクも発生します。
こうした制限を理解せずに運用を続けると、思わぬトラブルや追加コストにつながる可能性があります。赴任前に制度を確認し、代替手段を検討しておくことで安心して資産運用を続けられるでしょう。
現地金融機関の信頼性や言語の壁
海外駐在中に資産運用を行う際、現地の金融機関を利用することは必須です。しかし、その信頼性を見極めるのは容易ではありません。日本のように金融庁が厳格に監督している国ばかりではなく、金融規制が緩やかな国もあり、倒産や不正リスクを抱えているケースもあります。
また、契約書や商品説明が現地の言語で提供されるのが一般的です。専門用語を正しく理解できなければ、不利な条件で契約してしまう可能性も高まります。さらに、カスタマーサポートも現地の言語対応のみという場合があり、トラブルが発生した際に解決まで時間を要することも少なくないでしょう。
こうした問題を避けるためには、国際的に実績のある金融機関を選ぶことや、信頼できるIFAや専門家を通じて契約するなど、慎重な判断やリスク回避の行動をとることが大切です。
詐欺まがいの運用商品に要注意
海外駐在員は安定収入があり、投資詐欺や高額手数料の商品に狙われやすい傾向があります。実際に「必ず利益が出る」「利回り保証」といった甘い誘い文句で契約を迫られるケースも少なくありません。
特に、保険型の投資商品や長期積立プランには、解約が難しかったり、手数料が極端に高かったりするものが存在します。こうした商品に安易に手を出すと、元本割れや資産凍結といった大きな損失につながるリスクがあり、契約を検討する際は、運用実績や契約条件を必ず確認し、専門家や第三者の意見を聞くことが大切です。
帰国後も見据えた資産運用を今から準備しよう

海外駐在中の資産運用は、将来の教育資金や老後資金を準備するうえで大きな力となります。ただし、非居住者特有の制度制限や現地金融機関、万一のリスクを理解せずに始めてしまうと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
赴任中から長期的な戦略を立てることが重要です。海外での資産運用は、豊かな将来を築くための有効な手段です。しかし、適切な情報と戦略がなければリスクも伴います。
110Financial Supportでは、皆様のライフスタイルや目標に合わせた資産運用のサポートを行っています。疑問点やご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。私たちの専門知識を活かして、最適な運用方法を一緒に見つけましょう。
グローバルな保障設計と資産運用は、110(ワンテン)グループへ
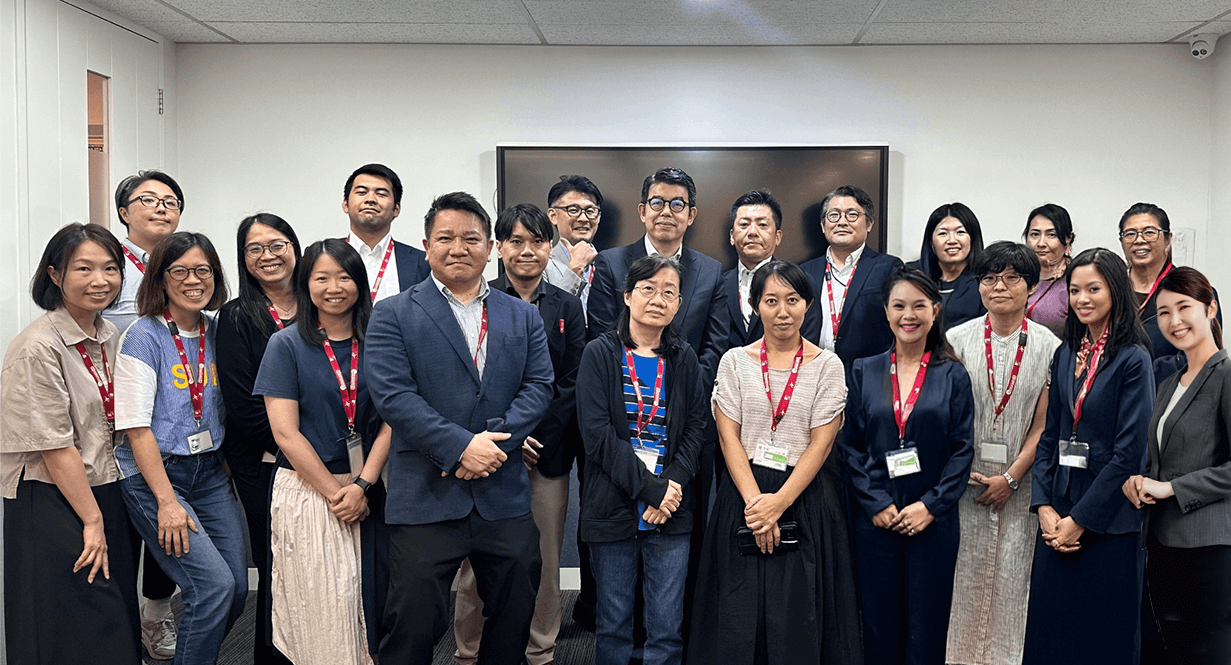
「110 Financial Support」では、海外在住者や海外移住を検討されている方の資産運用をサポートをしています。海外での資産運用では、資金シミュレーションはもちろん、税務知識の専門性や海外現地の情勢、物価上昇や想定外の出費など、多岐にわたる要因を考慮することが必要です。
- ・駐在国で、どのように資産運用すべきか、方法がわからない
- ・駐在から現地転職や現地起業に変わった場合の保障や資産運用を相談したい
- ・海外での資産運用事情や、老後資金の準備について詳しく知りたい
といったお困りごとがあれば、日本人サポート実績20年以上の「110 Financial Support」までご相談ください。海外在住者や海外移住前のご準備段階の方も、あなたの資産運用状況を踏まえ、最適な資産運用プランづくり・適正化のサポートをいたします。ぜひお気軽にご相談ください。
\海外保険 × 資産運用で新たなライフプランをご提案/
海外在住者のためのマネーセミナー開催中
Insurance110では世界各地に拠点があります。
各国に滞在する日本人ファイナンシャルプランナーが、海外在住時の資産運用に関するセミナーを行なっております。
老後2000万円問題や円安、物価高など家計に直結するニュースについても分かりやすく解説いたします。
\お金のプロに相談できる/
無料セミナー予約はこちら

